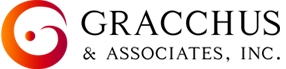代表・コンサルタント紹介

中里 肇 Hajime Nakazato
代表取締役
1988年日本長期信用銀行(現新生銀行)入行。
住専、リース、信販等ノンバンクの再生業務に長く関わる。
98年退職後は米系会計事務所PwCにて日本における金融債権流動化ビジネスをゴールドマン、モルガンスタンレーといった外資大手と共に推進。
2000年、当社設立。代表取締役に就任。
以後、M&Aや事業再生、不動産関連のコンサルティングサービスに幅広く従事。
国内外の大手金融機関のクライアント多数。
中央大学法学部卒
2015年10月1日
アビリーンのパラドックス
私達はここ数年、所謂「事業再生」の現場でアドバイザリーを実施してきた。
その殆どが取引銀行経由での依頼であるが、対象企業やメインバンクが様々な事情から主導的に「事業再生計画」の策定や実行ができない状況の中で、私達が当事者に代わりリーダーシップをとりつつ調整役も担う難しい役どころである。
「事業再生」を目指すこと自体に対する各ステークホルダーの「総論」は異なることは少ないが、やはり、実行段階での「各論」となると、片方の利益を優先すればもう片方の利益を損ねる事態が発生し、取りまとめは一筋縄ではない。
少しでも事態の収拾を早めるためには、やはり、対象企業の財務状態や資産のデュー・ディリジェンスを迅速且つ正確に行い、経済変化や対象企業を取り巻く環境を予測しつつ「再生計画」を策定し、今後の事業価値向上を目指し、経営者と共に「事業の再生」に向け格闘するしかない。
正確なデュー・ディリジェンスに裏打ちされ、夢物語りではない謙虚で合理的な「再生計画」であれば、遠からずコンセンサスを得る光明は見えてくる。
ただ、ここで気をつけなければならない点がもう一点ある。
銀行と対象企業、その他多くのステークホルダーとの打ち合わせを繰り返し実施する過程で、いつしか何とか穏便に取りまとめようという潜在意思が強くなりすぎ顕在化し、本来、自身が考えている「正しい道筋」を主張することを劣後させ、その場の雰囲気に迎合するような姿勢が出てくることである。
経営学にいう所謂「アビリーンのパラドックス」(注1)ともいえる現象で、本質的な議論は置き去りにされ、表面的な合意を取ることが優先されるものである。
これは、短期的には良くても中長期的に見ると、対象企業にも債権者にも決して利益をもたらすものではない。
「事業再生」が中途で頓挫する原因のかなりの部分がここにあると私は考えている。
プロセスの随所で、青臭い「そもそも論」を展開する必要がある。
「どうしてこの事業は再生すべきなのか」、「なぜ法的整理では駄目なのか」、「経営者はそのままでよいのか」、「M&Aは本当にシナジーを生むのか」、「債権カットはどの程度必要か」等々、議論の頭だしの段階で当事者間の不協和音が聞こえそうなテーマばかりである。特に、今日のようにコンプライアンス遵守が経営の最優先の時代には、失敗する確率が少なくない提案の出し手や「猫の首に鈴をつける」ようなトリガー役は誰しもやりたがらない。
しかし、リスクのない事業は有り得ない。神戸大学の砂川教授が最近の論文(注2)で、価値創造に結びつくリスクを「良いリスク」、価値創造を毀損するリスクを「悪いリスク」と分類しておられるように、難しい状況だからこそ、各ステークホルダーが自らの事業判断としてリスクを分析し決断しなければならない。
「ある8月の暑い日、テキサス州のある町である家族が団欒していた。そのうち一人が53マイル離れたアビリーンへの旅行を提案した。誰もがその旅行を望んでいなかったにもかかわらず皆他の家族は旅行をしたがっていると思い込み、誰もその提案に反対しなかった。
道中は暑く、埃っぽく、とても快適なものではなかった。提案者も含めて誰もアビリーンに行きたくなかったという事を皆が知ったのは旅行が終わった後だった。」(wikipedia) (注2)『日本経済新聞』 2015年9月7日朝刊「(経済教室)企業統治何が必要か 撤退の判断迫る体制を」 砂川伸幸 神戸大学教授
(注2) 『日本経済新聞』 2015年9月7日朝刊 「(経済教室)企業統治何が必要か 撤退の判断迫る体制を」 砂川伸幸 神戸大学教授
イソップのロバの親子
独裁的なリーダーシップは好ましくないものとして考えられる時代ではあるが、困難な問題を抱えている状況では、やはり強いリーダーの存在は不可欠である。
「事業再生」の現場では、それぞれの事情を抱えたステークホルダーが自己の利益を最大化すべく、あるいは損失を最小化すべく行動する。
たとえ、中長期的に見れば利益につながる可能性が高いことも目の前の不利益を飲み込んでまで理解することは難しい。
リーダーや調整役は、各ステークホルダーの利益をできるだけ優先すべく動くことは当然であるが、穏便に済ませようとするあまり、中途半端な判断になりうる危険性をはらんでいる。
イソップのロバの親子(注3)のように他人の意見に耳を傾けることに埋没し本質的な判断ができなくなっては本末転倒である。
一見、難しそうなアイデアでも、粘り強く主張し、時には独善的と取られかねないような強い判断、決断が必要な場合もある。
火中の栗を拾う
本来、リーダーシップをとるべき対象企業やメインバンクが、諸般の事情からその行動に出られないのであれば、やはり、それを代行できる立場の者、能力経験がある者が実行するしかない。
その役割は、時として、ステークホルダーの様々な思惑の中で批判に晒され、最近では訴訟のリスクも覚悟しなければならない局面もあるかもしれない。
私達は、それでも、果敢に直面する難問に向き合い、批判を懼れずに、火中の栗を拾うような行動をしながら、最終的には全てのステークホルダーが何とか納得できる最大公約数的な解を導き出していきたいと考えている。
私達が「事業再生」のビジネスを始めた頃は、単なるコーディネイター役になりかねない自分達の存在意義を疑う場面も多々あったが、実績を積み重ねた今日では、私達のような役回りがなければ決して「事業再生」の成功は有り得ないと実感するほどになって来ている。
ゴールへの道筋が見えにくいナローパスであればあるほど、私達の達成感は大きい。
これからも、日々精進しスキルアップを重ね、少しでもクライアントのお役に立てるよう頑張っていきたい。
メッセージ・アーカイブ
2024年07月「混沌から秩序へ」
2021年10月「ながらへば。。。」
2019年06月「手っ取り早く解を求めることの危うさ」
2018年10月「ラ・マンチャの男」
2015年10月「アビリーンのパラドックス」
2011年04月「東日本大震災において被災された皆さまに衷心よりお見舞い申し上げます」
2009年11月「米百俵」
2008年02月「グラックスがやってきたこと、今やっていること、これからやろうとしていること」
2006年02月「時代の変化と向き合う企業をサポートしたい 2」
2001年04月「時代の変化と向き合う企業をサポートしたい 1」
- グラックスについて
- 代表・コンサルタント紹介
- 会社概要
- ビジネスパートナー
- 著書紹介
- メディア掲載履歴